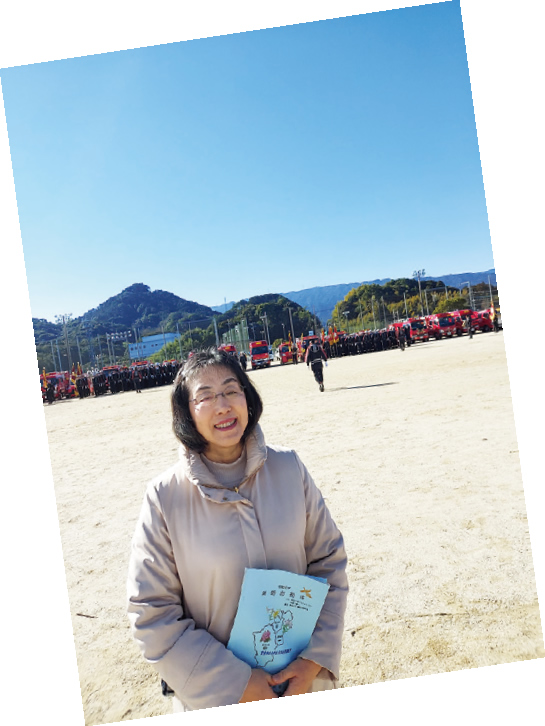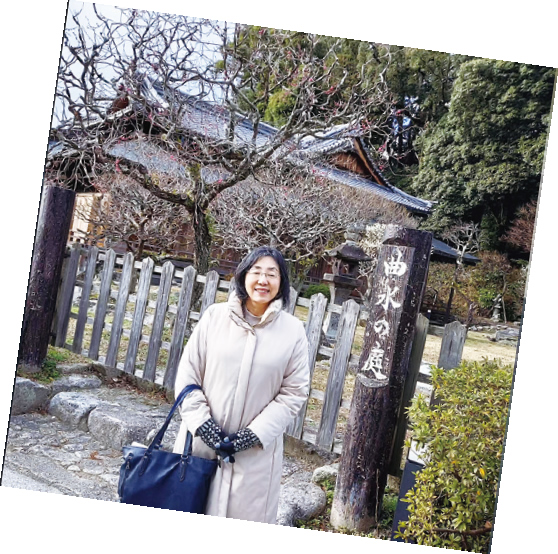大野城市議会議員 ながとし恭子 通信 2023年12月号
2024年が始まりました。本年もよろしくお願いいたします。
能登大地震、羽田空港の飛行機事故、北九州での火災など、今年の年明けは悲惨なニュースが続きました。被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
中でも能登大地震は、被害の大きさ、亡くなられた方の多さに言葉もありません。災害や事故発生から72時間(3日相当)が人命救助の勝負だと言われています。地震の多い日本には、政府の判断を要する自衛隊ではなく、専門の災害救助隊(レスキュー隊)の組織と装備の拡充が急務だと思いました。
そして、地震で心配されるのは原発事故です。放射能漏れがあれば避難や救助がさらに難しくなるからです。能登半島には志賀原発があります。通信が途絶えて放射線のデータが確認できなくなったり、油漏れや外部電源の一部が使えなくなったりしています。幸い2011年の福島原発事故以降停止中であったため惨事には至りませんでしたが、もし原発が動いていたらと思うと恐ろしくてなりません。住民の反対で作られませんでしたが、震源地間近の珠洲市に原発を作る計画もあったそうです。電力会社や政府の「大丈夫」という言葉は全く信用できないことがわかりました。原発には
使用済み核燃料が大量に保管されていて、稼働していなくても電気を使って冷やし続けなくてはなりません。稼働していなくても放射能漏れの危険はあります。災害救助隊には、放射線防護服も備え、専門の訓練をして、地震と原発事故の複合災害に備えておく必要もあると思います。
私たちの生命、財産、暮らしを守るために、政治(≒税金を何に使うか)に目を向け、暮らしの声を届けましょう!
現在の健康保険証の存続を求める請願書の採択に向けて賛成討論を行いました。
政府はマイナ保険証(電子カード)だけにして現在の健康保険証を廃止する方針です。しかし、マイナ保険証は、保険者情報が正しく反映されていなかったり、カードリーダーで読み取りができなかったり、トラブルがいまだに続いています。現在の健康保険証は、マイナ保険証でトラブルが起きたときにセーフティーネットの役割を果たしていて、保険診療を受けられないことを防ぎ、誤った情報による医療事故を防いでいます。なのに、マイナ保険証だけにしようとする政府の強引なやり方は、任意であるはずのマイナンバーカードを強制する手段として利用しているとしか思えません。
総務政策委員会で賛成の立場で発言しましたが、委員会での採決は賛成3反対3、しかし委員長が理由を示さないまま反対し、請願が委員会で否決され、本会議でも私は賛成討論を行いましたが、反対多数で否決されてしまいました。
災害等を考慮した選挙制度の見直しに関する意見書案に反対しました。
この意見書は、12月議会最終日に、自民党、公明党、日本維新の会の議員から提出されました。
豪雨災害などで選挙を行うことが困難な場合に任期延長をも可能とする抜本的な選挙制度改革を要望するもので、一見問題が無いように見えます。しかし、これは“憲法改正”を目指す憲法審査会の動きに連動しています。参議院の任期は6年、衆議院は4年と憲法に規定されていて、国会議員の任期延長のためには憲法の規定を変える必要が出てくるからです。
日本弁護士連合会は2023 年5月に『国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対し、大規模災害に備えるための公職選挙法の改正を求める意見書』を出しています。
任期延長ではなく、「選挙自体を延期する制度」や避難先でも投票できる「インターネット投票」など「災害に強い選挙制度」が先だと思います。
![]() 一般質問
一般質問
令和5年第5回12月定例会(3日目)⑦永利恭子
![]() わが国のジェンダーギャップ指数は、146 か国中125 位と低いことを問題と考え質問しました。
わが国のジェンダーギャップ指数は、146 か国中125 位と低いことを問題と考え質問しました。
<本市の正規職員の男女比>
一般職の正規職員( 令和5年4月1日現在の状況)
人数は、男性264 名、女性172 名の計436 名
割合は、男性が約61%、女性が約39%
<本市の幹部(部長級)職員の男女の状況>
部長級12名は全て男性( 令和5年4月1日現在)
<係長級以上の管理監督職の男女比と人数>
課長級は男性41名 (約79%)、女性11名 (約21%)
係長級は男性77名 (約76%)、女性24 名 (約24%)
<係長以上の管理監督職に占める女性職員の割合>
平成17年約13.1% → 令和5年約21.2%約1.6 倍
<過去3年間の新規採用職員における女性の割合>
約56.8%
<一般行政職に占める女性職員の割合>
平成17年約28% → 令和5年約39.4%
【問】市職員における女性管理職(部長・課長級)の割合の
目標値18%は少ないのでは?
【答】管理職になることを見込まれる50 歳以上の職員の女
性の割合が約18%となる実態から、同等を目指して、18%という目標を設定している。
![]() 女性活躍推進法に基づく本市の「職員の給与の男女の差異の情報」において
女性活躍推進法に基づく本市の「職員の給与の男女の差異の情報」において
【問】本市の全職員に係る男女の給与の差異は63.1%と近隣他市に比べても低い割合になっている。なぜか?
【答】相対的に給与水準が低くかつ女性の割合が多い会計年度任用職員の割合が、筑紫地区他市と比較して多いことから、結果として低い割合となっている。
【問】ハローワークの求人票には、従業員数1,130人、うち女性560人、従業員のうちパート270人と書かれていた。非正規職員が増えたのはいつ頃からか?
【答】令和5年度は、会計年度任用職員のフルタイムが252名、パートタイムが312名で、計564名となっており年々増加していて、特に直近の5年間で顕著に増加傾向にある。
![]() 中学校の給食アンケート
中学校の給食アンケート
【問】偏りが生じないアンケートを実施できるか?
【答】中学生の食事に関するアンケートは、中学生の食に関する全般の実態を把握し、その後の指導にすることを目的(選択制給食のアンケートではない)に、全生徒とその保護者、全教職員を対象に実施。保護者にはQRコードを記載した案内を配布し、スマートフォンなどで回答できる。学校の安心メールからも保護者に案内を発信し、より多くの保護者に回答いただけるよう取り組む。無記名により個人を特定できない形式で実施。自由記述欄を設け、中学校給食に関する様々な意見を記入いただけるよう工夫。
![]() 本市の新規採用職員の研修について
本市の新規採用職員の研修について
【問】研修先に自衛隊があるというのは本当か?
【答】目指すべき職員像の一つ市民に信頼され安心感を与えられる職員であるために、規律、挨拶、時間を守る等を身につけることを目的として、新規採用職員を対象に自衛隊での規律訓練を実施している。なお、地域活動インターンシップ研修、職場内研修であるOJT 研修等を通して、職員の対人コミュニケーション能力や対応力の強化に努めている。
PHOTOGRAPH
1962年 筑紫野市出身 / 1981年 福岡県立筑紫丘高校卒業 / 1986年 九州大学法学部卒業
1986年 福岡県庁入庁 総務部管財課 出納事務局総務課 嘉穂福祉事務所 総務部人事課勤務
1998年3月 福岡県庁退職
2010年~2017年 福岡市就労自立支援センター勤務(NPO法人福岡すまいの会)
2017年~2019年 公益社団法人福岡県保育協会勤務

⑦永利恭子議員-YouTube.png)